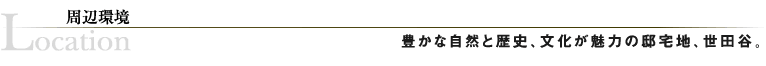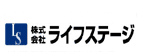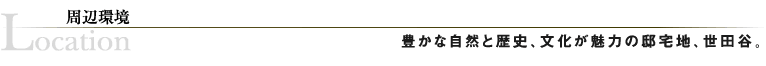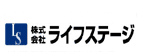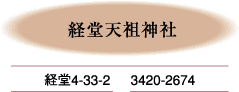 |
 古色深い天祖神社で、祭神は天照大神・宇迦御魂神・菅原道真公です。もとは「伊勢の宮」といわれていましたが、明治時代中頃、祀られている神様・天照大神の「天」と、氏神・先祖の神様の「祖」を合わせて天祖神社となりました。鳥居をくぐると、右側に小さな祠があります。これは三峯社といい、お使いはお犬様です。 古色深い天祖神社で、祭神は天照大神・宇迦御魂神・菅原道真公です。もとは「伊勢の宮」といわれていましたが、明治時代中頃、祀られている神様・天照大神の「天」と、氏神・先祖の神様の「祖」を合わせて天祖神社となりました。鳥居をくぐると、右側に小さな祠があります。これは三峯社といい、お使いはお犬様です。 |
|
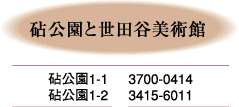 |
 砧公園は、「家族ぐるみで楽しめる公園」をテーマに造成された大規模なファミリーパークです。豊かな緑にあふれ、野球場兼競技場やアスレチック広場などの運動施設を備えています。その一角に世田谷美術館があり、年間を通して、区ゆかりの美術家の作品の展示や幅広い分野の芸術を紹介する企画展などを開催しています。 砧公園は、「家族ぐるみで楽しめる公園」をテーマに造成された大規模なファミリーパークです。豊かな緑にあふれ、野球場兼競技場やアスレチック広場などの運動施設を備えています。その一角に世田谷美術館があり、年間を通して、区ゆかりの美術家の作品の展示や幅広い分野の芸術を紹介する企画展などを開催しています。 |
|
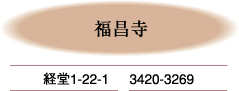 |
 江戸時代の中頃、周辺の村で悪病が流行し死亡者が続出しました。そこで、当時の住職が方々から寄付を集めて百体観世音を作り祀ったところ、悪病が癒えたという言い伝えが残っています。年に数回、地元の人たちによる「経堂音楽の夕べ」という会が開催されるなど、地域と密着したお寺です。 江戸時代の中頃、周辺の村で悪病が流行し死亡者が続出しました。そこで、当時の住職が方々から寄付を集めて百体観世音を作り祀ったところ、悪病が癒えたという言い伝えが残っています。年に数回、地元の人たちによる「経堂音楽の夕べ」という会が開催されるなど、地域と密着したお寺です。 |
|